○砂川市公用文に関する規程
昭和35年9月1日訓令第7号
改正
昭和39年5月7日訓令第3号
昭和42年7月28日訓令第7号
昭和58年12月30日訓令第9号
平成元年3月24日訓令第5号
平成22年12月1日訓令第20号
砂川市公用文に関する規程
(目的)
第1条 本市公用文の文体、用字、用語、形式及び配字については特別の定めがあるもの
を除くほか、この訓令の定めるところによる。
(文体)
第2条 公用文は、やさしく、美しく、そして耳で聞いても意味のわかるようにしなけれ
ばならない。
(1) 公用文に用いる文体は、原則として「ます」体とする。ただし、法規文書、令達
文書、公示文書及び一般文書のうち議案、契約書等に用いる文体は、様式の部分を除
き、「である」体とする。
(2) 従来の文語体の形式にとらわれずに、口語文として自由な表現で日常一般に使わ
れているやさしいことばを用いる。
(3) 全体に統一ある文章として、長すぎて読みにくくならないよう接続詞を用いて、
文章を適当に区切るようにする。
(4) 文章の標題は、平易簡単にして「○○○に関する件」は「○○○について」のよ
うにする。
(用字用語)
第3条 文字は、漢字と平仮名を交えて用いる。ただし、外国の人名、地名、又は借用語、
その他特に示す必要があるものは、片仮名を用いる。
2 漢字、仮名遣い及び送り仮名は、次の各号に掲げる範囲によることとし、誤解の多い
漢語及び略語はさける。ただし、人名、地名等でこれによることができないものは、そ
の定まっているものによることができる。
(1) 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)
(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)
(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)
(4) 公用文における漢字使用等について(平成22年内閣訓令第1号)
(5) 「公用文における漢字使用等について」の具体的な取扱い方針について(昭和56
年内閣第150号、庁文国第19号)
(6) 法令における漢字使用等について(平成22年内閣法制局長官)
(7) 法令用語改正要領(昭和29年法制局総発第89号)
3 一般的な用字用語の使い方は次のとおりとする。
(1) 漢字に振り仮名をつける場合は、その字の上に書く。
(2) 数字は(3)に掲げる場合を除き、アラビヤ数字を用いる。
ア 数字のけたの区切りは3位区切りとし、区切り点は、「,」を用いる。ただし、
年号、文書番号、電話番号等の特別なものは区切りをつけない。
イ 小数、分数及び帯分数の書き方は次の例による。
例 |
|
よい |
わるい |
|
小数 |
0.963 |
0,963 |
|
分数 |
 |
1/2 |
|
帯分数 |
 |
11/2 |
|
ウ 日時、時刻及び時間の書き方は次の例による。
例 |
|
日時 |
時刻 |
時間 |
普通の場合 |
昭和36年1月1日 |
9時05分 |
10時15分 |
5時間
30分 |
省略する場合 |
昭和35・3・1 |
9・05 |
22・15 |
|
35・3・1 |
|
|
|
(3) 漢数字は次のような場合に用いる。
ア 固有名詞 例:四国 二重橋
イ 概数を示す語 例:四、五日 二、三名 数十日
ウ 数量的な意味のうすい語 例:一部分 一般的 四捨五入
エ 慣用的な語 例:一休み 二言目
オ けたの大きい数の単位として用いる場合
よい |
わるい |
|
120万円 |
12万5千円 |
|
9,400億 |
3千円 |
|
125,000円 |
6百人 |
|
ただし、単位千円という使い方はよい。
(4) 記号の用い方は、おおむね次のとおりとする。
ア 句読点
まる「。」、コンマ「,」及びてん「、」を用い、コンマ「,」はこのほかに数
字の区切りに用いる。
イ ピリオド「.」
単位を示す場合、見出し記号につける場合及び省略符号とする場合に用いる。
例:0.05 1. 昭.36.1.1
ウ コロン「:」
次にとく説明文、又は、その他の語句がある場合に用いる。
 電話:砂川.400
エ なみがた「〜」
時・所・数量・順序などを継続的に
電話:砂川.400
エ なみがた「〜」
時・所・数量・順序などを継続的に を示す場合に用いる。
例:砂川〜札幌 4〜5日
4,500万円〜1億3,000万円
第1号〜第5号
オ ダツシユ「―」
語句の説明、言いかえ、又は丁目、番地を省略して書く場合に用いる。
例:赤色―国道 青色―市道
例規―条例。規則。規程
東1条北1―1(東1条北1丁目1番地)
カ 括弧( )
( )と
を示す場合に用いる。
例:砂川〜札幌 4〜5日
4,500万円〜1億3,000万円
第1号〜第5号
オ ダツシユ「―」
語句の説明、言いかえ、又は丁目、番地を省略して書く場合に用いる。
例:赤色―国道 青色―市道
例規―条例。規則。規程
東1条北1―1(東1条北1丁目1番地)
カ 括弧( )
( )と 又は「 」を縦書きの場合と同様に用い特に必要があるときは『 』
〔 〕{ }を用いる。
キ くりかえし符号は、必要に応じ漢字が続くときは「々」を用い、同じ仮名が続く
ときは同じ仮名を続けて書く。
又は「 」を縦書きの場合と同様に用い特に必要があるときは『 』
〔 〕{ }を用いる。
キ くりかえし符号は、必要に応じ漢字が続くときは「々」を用い、同じ仮名が続く
ときは同じ仮名を続けて書く。
よい |
わるい |
|
別々、いろいろ、たびたび |
つぎ々、べつゞゝ |
|
ク 傍点及び傍線は、必要に応じて傍点は語句の上に、傍線は語句の下に書く。
(5) 見出し記号の用い方は、項目を細別するときに次のような順序で用いる。(仮名
は、五十音順に用いる。)
ア 一般文書の場合 |
イ 例規の場合 |
1 ・・・・・・ |
第1 (章、節、条) |
(1) ・・・・・ |
1 (項)・・・・・・ |
ア ・・・・ |
(1) (号)・・・・・ |
(ア) ・・・ |
ア ・・・・・・ |
(ア) ・・・・・ |
(敬称)
第4条 公用文の名あて人に付ける敬称は、「様」とする。ただし、文書の内容、形式等
から他の敬称を用いた方が適当と認められる場合又は法令等に特別の定めがある場合は、
他の敬称を用いることができる。
(形式)
第5条 公文書の形式及び配字は、おおむね次のとおりとする。
1 条例の形式及び配字(規則、規程はこれに準ずる。)
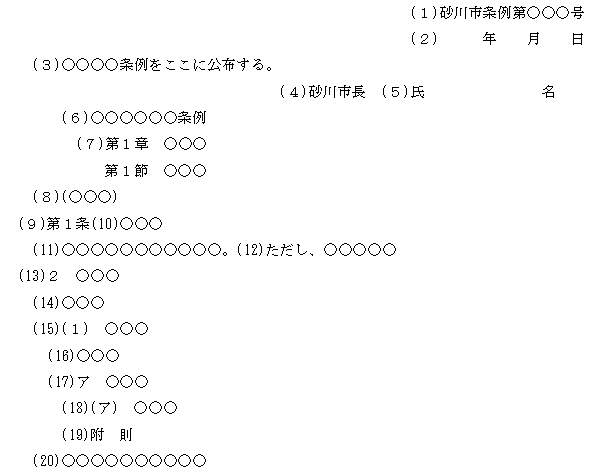 改正廃止の場合もこれに準ずる。
(1) 条例番号の初字は、末尾から11字目とする。
(2) 公布年月日の初字は、末尾から11字目とする。
(3) 公布文の初字は、第2字目からとする。
(4) 市長名の初字は、末尾から19字目とする。
(5) 1字あける。
(6) 題名の初字は第4字目から、2行以上にわたるときも同じとする。
(7) 章名の初字は第5字目からとし、章名と章の文との間は1字あける。節名の初字
は、章名の1字右よりとする。
(8) 見出し括弧は、第2字目からとする。
(9) 第1字目とする。
(10) 条名と本文との間は1字あける。
(項、号、ア、(ア)の場合も同様とする。)
(11) 第2字目とする。
(12) ただし書は、本文と接続させる。
(13) 第1字目とする。
(14) 第2字目とする。
(15) 第2字目とする。
(16) 第3字目とする。
(17) 第3字目とする。
(18) 第4字目とする。
(19) 附則の初字は第4字目とし、附と則の間は1字あける。
(20) 附則の本文は、第2字目とする。
2 訓令の形式及び配字
改正廃止の場合もこれに準ずる。
(1) 条例番号の初字は、末尾から11字目とする。
(2) 公布年月日の初字は、末尾から11字目とする。
(3) 公布文の初字は、第2字目からとする。
(4) 市長名の初字は、末尾から19字目とする。
(5) 1字あける。
(6) 題名の初字は第4字目から、2行以上にわたるときも同じとする。
(7) 章名の初字は第5字目からとし、章名と章の文との間は1字あける。節名の初字
は、章名の1字右よりとする。
(8) 見出し括弧は、第2字目からとする。
(9) 第1字目とする。
(10) 条名と本文との間は1字あける。
(項、号、ア、(ア)の場合も同様とする。)
(11) 第2字目とする。
(12) ただし書は、本文と接続させる。
(13) 第1字目とする。
(14) 第2字目とする。
(15) 第2字目とする。
(16) 第3字目とする。
(17) 第3字目とする。
(18) 第4字目とする。
(19) 附則の初字は第4字目とし、附と則の間は1字あける。
(20) 附則の本文は、第2字目とする。
2 訓令の形式及び配字
 (1) 訓令番号及び日付は、末尾から11字目とする。
(2) 第2字目からとする。
(3) 市長名の初字は、末尾から19字目とし、市長の補助職員名で通達する場合も同様
に職氏名を記して(6)を付する。
(4) 初字は第4字目とする。
(5) 第2字目からとし、第2行目の初字は、第1字目とする。
(6) 第2字目からとする。
3 告示の形式及び配字
(1) 訓令番号及び日付は、末尾から11字目とする。
(2) 第2字目からとする。
(3) 市長名の初字は、末尾から19字目とし、市長の補助職員名で通達する場合も同様
に職氏名を記して(6)を付する。
(4) 初字は第4字目とする。
(5) 第2字目からとし、第2行目の初字は、第1字目とする。
(6) 第2字目からとする。
3 告示の形式及び配字
 (1) 告示番号の初字は、末尾から11字目とする。
(2) 初字は、第4字目とする。
(3) 第2字目からとする。
(4) 第3字目からとする。
(5) 初字は、末尾から19字目とする。
4 指令の形式及び配字
(1) 告示番号の初字は、末尾から11字目とする。
(2) 初字は、第4字目とする。
(3) 第2字目からとする。
(4) 第3字目からとする。
(5) 初字は、末尾から19字目とする。
4 指令の形式及び配字
 (1) 初字は、主管課、所、係の頭文字(砂庶務等のごとく)を記入し、末尾から11字
目とする。
(2) 第2字目からとする。
(3) 末尾から19字目とする。
(4) 第2字目からとし、第2行目からは第1字目からとする。
(5) 第2字目からとする。
5 議案の形式と配字
(1) 初字は、主管課、所、係の頭文字(砂庶務等のごとく)を記入し、末尾から11字
目とする。
(2) 第2字目からとする。
(3) 末尾から19字目とする。
(4) 第2字目からとし、第2行目からは第1字目からとする。
(5) 第2字目からとする。
5 議案の形式と配字
 条例の設定及び改廃又は同意(承認)を求めるもの、その他買収、認定等の場合もこれ
に準ずる。
(1) 第1字目からとし、表面は左側に裏面は右側に書く。
(2) 第4字目からとする。
(3) 第2字目からとする。
(4) 第3字目からとする。
(5) 市長名の初字は、末尾から19字目とする。
(6) 記の場合は、第12字目とし、件名の場合は、第4字目からとする。
(7) 第2字目からとする。
(8) 第2字目からとする。
6 一般文書の形式と配字
条例の設定及び改廃又は同意(承認)を求めるもの、その他買収、認定等の場合もこれ
に準ずる。
(1) 第1字目からとし、表面は左側に裏面は右側に書く。
(2) 第4字目からとする。
(3) 第2字目からとする。
(4) 第3字目からとする。
(5) 市長名の初字は、末尾から19字目とする。
(6) 記の場合は、第12字目とし、件名の場合は、第4字目からとする。
(7) 第2字目からとする。
(8) 第2字目からとする。
6 一般文書の形式と配字
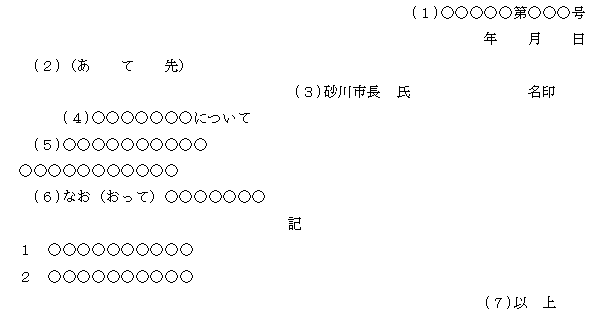 用紙の大小によらずこの形式とする。
(1) 初字は、主管課、所、係の頭文字(砂庶務のごとく)記入し、末尾から11字目と
する。
(2) 第2字目からとする。
(3) 末尾から19字目とする。
(4) 第4字目からとする。
(5) 第2字目からとし、第2行目からは第1字目からとする。
(6) 第2字目からとする。
(7) 文書の終りは必ず「以上」と書く。
附 則
この規程は、昭和36年1月1日から施行する。
附 則(昭和39年5月7日訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和39年4月4日より適用する。
附 則(昭和42年7月28日訓令第7号抄)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年12月30日訓令第9号)
この訓令は、昭和59年1月1日から施行する。
附 則(平成元年3月24日訓令第5号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月1日訓令第20号)
この訓令は、平成22年12月1日から施行する。
別表
用紙の大小によらずこの形式とする。
(1) 初字は、主管課、所、係の頭文字(砂庶務のごとく)記入し、末尾から11字目と
する。
(2) 第2字目からとする。
(3) 末尾から19字目とする。
(4) 第4字目からとする。
(5) 第2字目からとし、第2行目からは第1字目からとする。
(6) 第2字目からとする。
(7) 文書の終りは必ず「以上」と書く。
附 則
この規程は、昭和36年1月1日から施行する。
附 則(昭和39年5月7日訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和39年4月4日より適用する。
附 則(昭和42年7月28日訓令第7号抄)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年12月30日訓令第9号)
この訓令は、昭和59年1月1日から施行する。
附 則(平成元年3月24日訓令第5号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月1日訓令第20号)
この訓令は、平成22年12月1日から施行する。
別表

電話:砂川.400 エ なみがた「〜」 時・所・数量・順序などを継続的に
を示す場合に用いる。 例:砂川〜札幌 4〜5日 4,500万円〜1億3,000万円 第1号〜第5号 オ ダツシユ「―」 語句の説明、言いかえ、又は丁目、番地を省略して書く場合に用いる。 例:赤色―国道 青色―市道 例規―条例。規則。規程 東1条北1―1(東1条北1丁目1番地) カ 括弧( ) ( )と
又は「 」を縦書きの場合と同様に用い特に必要があるときは『 』 〔 〕{ }を用いる。 キ くりかえし符号は、必要に応じ漢字が続くときは「々」を用い、同じ仮名が続く ときは同じ仮名を続けて書く。
改正廃止の場合もこれに準ずる。 (1) 条例番号の初字は、末尾から11字目とする。 (2) 公布年月日の初字は、末尾から11字目とする。 (3) 公布文の初字は、第2字目からとする。 (4) 市長名の初字は、末尾から19字目とする。 (5) 1字あける。 (6) 題名の初字は第4字目から、2行以上にわたるときも同じとする。 (7) 章名の初字は第5字目からとし、章名と章の文との間は1字あける。節名の初字 は、章名の1字右よりとする。 (8) 見出し括弧は、第2字目からとする。 (9) 第1字目とする。 (10) 条名と本文との間は1字あける。 (項、号、ア、(ア)の場合も同様とする。) (11) 第2字目とする。 (12) ただし書は、本文と接続させる。 (13) 第1字目とする。 (14) 第2字目とする。 (15) 第2字目とする。 (16) 第3字目とする。 (17) 第3字目とする。 (18) 第4字目とする。 (19) 附則の初字は第4字目とし、附と則の間は1字あける。 (20) 附則の本文は、第2字目とする。 2 訓令の形式及び配字
(1) 訓令番号及び日付は、末尾から11字目とする。 (2) 第2字目からとする。 (3) 市長名の初字は、末尾から19字目とし、市長の補助職員名で通達する場合も同様 に職氏名を記して(6)を付する。 (4) 初字は第4字目とする。 (5) 第2字目からとし、第2行目の初字は、第1字目とする。 (6) 第2字目からとする。 3 告示の形式及び配字
(1) 告示番号の初字は、末尾から11字目とする。 (2) 初字は、第4字目とする。 (3) 第2字目からとする。 (4) 第3字目からとする。 (5) 初字は、末尾から19字目とする。 4 指令の形式及び配字
(1) 初字は、主管課、所、係の頭文字(砂庶務等のごとく)を記入し、末尾から11字 目とする。 (2) 第2字目からとする。 (3) 末尾から19字目とする。 (4) 第2字目からとし、第2行目からは第1字目からとする。 (5) 第2字目からとする。 5 議案の形式と配字
条例の設定及び改廃又は同意(承認)を求めるもの、その他買収、認定等の場合もこれ に準ずる。 (1) 第1字目からとし、表面は左側に裏面は右側に書く。 (2) 第4字目からとする。 (3) 第2字目からとする。 (4) 第3字目からとする。 (5) 市長名の初字は、末尾から19字目とする。 (6) 記の場合は、第12字目とし、件名の場合は、第4字目からとする。 (7) 第2字目からとする。 (8) 第2字目からとする。 6 一般文書の形式と配字
用紙の大小によらずこの形式とする。 (1) 初字は、主管課、所、係の頭文字(砂庶務のごとく)記入し、末尾から11字目と する。 (2) 第2字目からとする。 (3) 末尾から19字目とする。 (4) 第4字目からとする。 (5) 第2字目からとし、第2行目からは第1字目からとする。 (6) 第2字目からとする。 (7) 文書の終りは必ず「以上」と書く。 附 則 この規程は、昭和36年1月1日から施行する。 附 則(昭和39年5月7日訓令第3号) この規程は、公布の日から施行し、昭和39年4月4日より適用する。 附 則(昭和42年7月28日訓令第7号抄) 1 この規程は、公布の日から施行する。 附 則(昭和58年12月30日訓令第9号) この訓令は、昭和59年1月1日から施行する。 附 則(平成元年3月24日訓令第5号) この訓令は、平成元年4月1日から施行する。 附 則(平成22年12月1日訓令第20号) この訓令は、平成22年12月1日から施行する。 別表