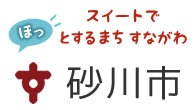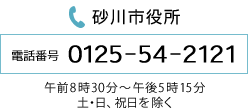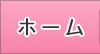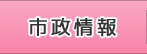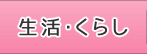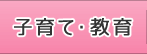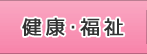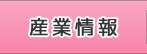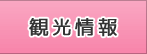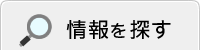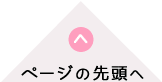9月23日は「手話言語の国際デー・手話の日」です
手話言語の国際デー
毎年、9月23日は「手話言語の国際デー」です。
手話言語の国際デーは、平成29年(2017年)12月19日に国連総会で決議されました。決議文では、手話言語が音声言語と対等であることを認め、ろう者の人権が完全に保障されるよう国連加盟国の社会全体で手話言語についての意識を高める手段を講じることを促進するとされています。また、9月23日は 昭和26年(1951 年)に世界ろう連盟(World Federation of the Deaf:WFD)が設立された日でもあります。
手話に関する施策の推進に関する法律・手話の日
「手話に関する施策の推進に関する法律」が、令和7(2025)年6月25日に公布され、同日施行されました。法律では、手話の習得及び使用に関する施策や手話文化の保存、継承及び発展に関する施策、並びに手話に関する国民の理解と関心の増進を図るための施策に関して基本理念を定めました。また、手話の習得や手話を使って暮らせる環境整備等を国や自治体の責務であることが明記されるとともに、手話に関する施策を総合的に推進することを目的としています。国民の間に広く手話に関する理解と関心を深めるようにするため、国内においても9月23日を「手話の日」と定めました。
手話とは?
手話は、ろう者がコミュニケーションをとったり物事を考えたりするときに使うことばで手首の動きや表情などを使って概念や意思を視覚的に表現する視覚言語であり、ろう者の母語です。手話は、日本語とは異なる言語で、独自の語彙や文法体系を持っている言語です。日本語や英語等さまざまな言語があるように、世界各国でそれぞれ異なる語彙や文法体系を持っています。
砂川手話の会
市内で活動している砂川手話の会の例会に市職員が参加しましたので、活動の様子をご紹介します。砂川手話の会では、毎週火曜日18時から公民館1階第2研修室で学習会を行っています。現在、会員は15名で、手話を始めて数か月の方から30年以上のベテランの方もおり、年齢層も幅広く、近隣の町から参加されている方もいらっしゃいます。
学習会では、手や指の動きを確認するため事前にビデオで確認した後、2人一組となり手話で会話をするシミュレーション形式で行われましたが、完成度の高い手話と顔の表情も豊かに会話を行う皆さんの姿に、正直、圧倒されてしまいました。また、学習部長の渡辺さんから、「近年は多様化の時代で、男性や女性という性別の違いを表す表現もされなくなってきている」というお話が印象的で、手話も日々進化を続けていると感じました。




会員の臼杵さんからお話を伺ったので、ご紹介します。

夫の転勤で今年の3月に砂川に引っ越してきました。以前、看護師をしていた際に聴覚障がいの方とお話する機会があり、その時は筆談で行ったのですが、手話を用いて会話をしてみたいなと思ったことがきっかけで、5月にこの会に参加しました。入会当初は、わからないことも多くて、皆さんに付いていくだけでも大変だったのですが、参加していく中で手話を使って会話が出来るようになったときや皆さんから褒めていただいたときには、とてもうれしく感じます。また将来、看護師として働く際に、手話を使って会話が出来ることを目標に日々頑張りたいです。
手話は、聞こえる人たちが話す言葉以上にとても奥深いものです。手話で会話ができた時、きっとみなさんも感動を受けると思います。砂川手話の会は、初心者の方も歓迎されているとのことです。まずは、見学から始めてみませんか?
図書館に聴覚障がいの特設コーナーを開設します
10月1日から図書館において、聴覚障がいに係る図書の特設コーナーを開設します。手話に関する本も揃えていますので、ぜひ、この機会にご覧ください。
お問い合わせ先
砂川市 保健福祉部 社会福祉課 社会福祉係〔1階 13番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8103 FAX 0125-55-2301
お問い合わせフォーム